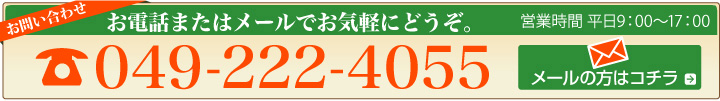| 父親の相続を機に先々代名義の不動産(土地)を遺産分割により承継した事例>> |
| 遺留分の減殺請求した相続人が相続税の申告期限前にお亡くなりになってしまった事例>> |
農家のご相続。財産を調査しているところで、自宅敷地の一部が被相続人(父親)の先々代名義のまま存続していることが判明。当時相続はしていたと思われるが、名義については農家の自宅の一部ということもあって、そのままにしていたものと考えられたが、書類がないため確認することはできなかった。自宅は市街化区域に位置することもあり、敷地の広さから考えても財産価値は高く、このまま放置すれば将来処分(売却)することも何もできなくなることが予想された。
相続人に現状をご説明し、被相続人(父親)に財産承継させ、本家の相続人が承継していただくこととした。
クリア-しなければならないハードルは、先々代の相続であり相続人も枝葉が別れ、遺産分割に名前を連ねる人数が相当数に及び、全員の合意が得られるかであったが、何のトラブルもなく全員から快く遺産分割協議書に押印いただくことができた。司法書士の先生いわく、「通常は2世代も前の相続ともなればお互い顔も知らず、問題となっている財産(不動産)さえ知らないため、相続人のうち誰かしらはヘソをまげ、遺産分割が成立するのは並大抵のことではないのに本当に奇跡だ。」
電話や手紙ではなく、相続人に直接お会いいただいて事情をご説明して下さいとアドバイスさせていただいた。お会いいただいたことで本家相続人の人柄のよさと真摯な態度が相手に通じることとなり、結果的には功を奏した形となった。本当は電話だけですませたかったけど会って本当によかったといっていただいた。
遺産分割も申告期限内に終わり、納税も滞りなく納めていただくことができ、ご相続人には大変喜んでいただくことができました。
弁護士からのご紹介案件。法定相続人は母親のみというご相続であったが、公正証書遺言が残されており、遺言内容は財産の大半はとある公益財団法人に寄付し、一部を甥に遺贈するという内容で、本来の相続人には財産承継はないというものであった。
ご相続人のご意志のもと、弁護士から遺留分の減殺請求が公益財団法人に対してなされた。遺留分の算定にあたり、相続財産の総額を早急に把握する必要があったが、遺言執行者の信託銀行の協力を得ながら資料収集、不動産評価を経つつ財産総額を把握することができた。
ご相続人、公益財団法人双方の弁護士で遺留分の金額をいくらにするか折衝を重ね、概ね合意が得られた。遺留分の金額がほぼ確定したことを受け、相続税を計算。今回相続税を申告いただく母親と甥の相続税及び納税方法を弁護士と相談していた矢先に相続人である母親が亡くなった。申告期限の半月前のことであった。
相続税の申告が必要な相続人が申告期限前に亡くなった場合は、当該相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に当該相続人の相続人が申告する義務を負うことになる。母親は、生前養子を迎い入れていたため、連絡をとった上で今後の手続きについて説明を行った。
申告期限は10か月先とはなるが、内容に変更がないのであれば、早めに申告をしてしまいたいとのご希望であった。
母親の生存中から、弁護士からは、遺留分の最終確定(遺留分合意書の取り交わし)は申告期限には間に合わないといわれていた。よって、当初のシナリオは遺留分の見込みで期限内申告をして、遺留分の最終確定時点で申告をし直す予定であった。
お亡くなりになったことで申告期限が伸びた。早速、弁護士に遺留分合意書の締結をお願いし、尽力いただいたことで本来の申告期限の1日前に合意が整った。
その結果、甥の申告書提出から遅れること1週間余りで母親の申告書も提出することができた。
このように早期に申告までこぎつくことができたのは、提携している士業の先生とのネットワ-クを通じワンストップで案件を処理することができたためであり、ご相続人には非常に喜んでいただけました。
相続に関することならお気軽に佐伯税務会計事務所の無料相談をご利用ください。